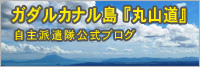第五回フィールドワーク予科練平和記念館
2010.10.30
フィールドワーク概要
■日時■ 2010年10月30日(土)
■場所■ 茨城県稲敷郡阿見町:予科練平和記念館
■参加人数■ 8名
フォトギャラリー
 予科練平和記念館は、リニューアルされたばかりでとってもキレイ。せいぜい1時間半程度の見学だろうと思っていたのですが、なんと3時間以上も滞在。皆、展示を熱心に見入っていました。 予科練平和記念館は、リニューアルされたばかりでとってもキレイ。せいぜい1時間半程度の見学だろうと思っていたのですが、なんと3時間以上も滞在。皆、展示を熱心に見入っていました。
|
 館内では、歴史調査員の戸張礼記さんが丁寧な説明をしてくださり、見学を終えてからも質問タイムを設けてくれました。 館内では、歴史調査員の戸張礼記さんが丁寧な説明をしてくださり、見学を終えてからも質問タイムを設けてくれました。
|
 霞月楼では、戦時中、この店を訪れた常連さんたちのツケを記した台帳が残って
いました。意外な人の名前があって、一同からどよめきが……。 霞月楼では、戦時中、この店を訪れた常連さんたちのツケを記した台帳が残って
いました。意外な人の名前があって、一同からどよめきが……。 |
 料亭に来た方々が書きなぐったついたて。よ~く見ると、女体の絵も……。
皆、普段は難しいことを考え、凛々しい姿を見せていても、酔っ払うと昔も今も変わらず? 料亭に来た方々が書きなぐったついたて。よ~く見ると、女体の絵も……。
皆、普段は難しいことを考え、凛々しい姿を見せていても、酔っ払うと昔も今も変わらず? |
フィールドワークレポート
参加者より一言
こうした類の記念館は、得てして戦争の「悲惨さ」を殊更強調しがちだが、この記念館にはそうしたところがなく、予科練があったことに阿見町の人々が誇りを持っていることが感じられた。ハンモックや勉強机等、練習生の生活が偲ばれる展示が興味深かった。
職員の説明に、この記念館に限ったことではないので「日中戦争」「太平洋戦争」は止むを得ないとしても、「15年戦争」という表現が出てきたのには抵抗を感じた。
戸張氏が予科練に入った動機の説明で「国を挙げての大キャンペーンがあり、飛行機乗りに憧れた。今の子供達が野球選手やタレントに憧れるのと同じだ」と言っていたが、他方で「当時は皆一所懸命だった」「何くそ負けるものか、と思った」とも言っていた。また戦争が終わったとき「これで家に帰れるという嬉しさが抑えきれなかった。故郷への思いは経験しなければ分からない」とも言っていた。当時の練習生の正直な気持ちが聞けた思いがした。最後の「平和は守らなければならない」という言葉が印象的だった。
【水野靖夫】
先立つ十月三十日、台風14号の来る最中、PandA会有志は茨城県稲敷市阿見町にある海軍予科練平和記念館へFWに訪れた。私は今回が初参加になる。入館前より会員の方々が「一つだけ直線の道路があるが、これは阿見坂管制道の名残だ」「平和記念館はおかしい。堂々と戦争記念館にすべきだ」等と意気高揚させていた。記念館は『入隊』『訓練』『心情』『飛翔』『交流』『窮迫』『特攻』の七部構成になっていて、まだ十六~八歳の幼い予科練生の写真を飾りながら、彼らの短い生涯を映していた。博学な案内の女性と予科練生生き残りの戸張礼記さんに導かれて館内を見学する。戦争を考える後生として、さほど偏ってない展示が嬉しい。何より生活と戦争を一緒にして、兵士と学生の両面を表しているのが良かった。戸張さんが「十五年戦争、天皇より家族の為」と数度か仰ったが、これもマスコミの影響だろうか。台風のせいで離れの雄翔館に入れなかったのが残念。
【木村留以】
去る平成22年10月30日より一泊で待望のフィールドワーク、『予科練平和記念館』を訪問した。
まずは予科練出身の戸張礼記様に予科練のあらましをご説明頂く。氏は幸いにも、大東亜戦末期に入隊し、飛行機の生産が追い付かなかったために、陣地構築に従事させられていたところ敢え無く終戦を迎えたのである。いわく、「だから今、こうして皆さんにお話しすることが出来るのです。」と。無性に有り難かった。
入営、訓練、生活、手紙、出撃と順を追って館内を見入る。私ははじめのブースに入り一つの小さな展示品に度胆を抜かれた。
予科練は『懇切丁寧』であったのである。
それは入隊に際して、分隊長から発信される保護者宛の印刷物を見て伺える。現代で言うならば、A4版一枚の手紙に、所狭しと文字が羅列されている。それは部隊編成、教育方法、生活面、食事、衛生、給与、金銭、面会、音信(手紙のやりとり)、帰省について事細かに記しているのである。
いわば天下の予科練が、本来機密事項であろう部隊編成から、教育の仕方、毎度のご飯や医療、果てはお小遣いのこと、子供さんとの面会にまで長々と説明しているのである。そして極め付けはこれである。文章を写して来た。
「入隊後ハ本人ノ身ノ上ニ関シ御不審ノ点アラバ直チニ分隊長ニ連絡相成度。本人指導上、参考トナルベキ事項等御遠慮ナク御申越相成度。」
何かあったらおっしゃって下さいと言っているのである。世が世であれ、親は親である。子供の心配をしない親はどこにも居ない。今のようにモンスターペアレンツが居ない良き時代ではあるが、この説明を読んで、一度は息子のことを分隊長に問い合わせた両親も居たのではないかと。
とかく陸海軍に関して悪く思う方々にもこの予科練平和記念館をご覧頂きたい。帝国海軍は、ちゃんと親子の関係を取り持ちながら、丁寧且つ謙虚に親への説明を記している。当時のどこに、ここまで記す軍隊が世界にあったであろうか。今まで知り得なかった大変貴重な『お土産』を頂いた。
我々は若くして散華された英霊に、これからもずっと手を合わせるのみである。
最後に戸張様はじめ館内の皆様に、丁重なるご対応に深謝申し上げます。
【崎津寛光】
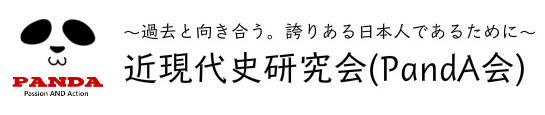

 HOME
HOME PandA会とは
PandA会とは 活動報告
活動報告 戦跡アルバム
戦跡アルバム お問合わせ
お問合わせ